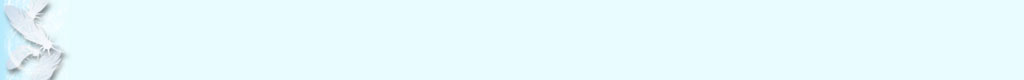「駄目だ、もう何も出てこない」
悲壮感漂う声を作って、友に告げる。
しかし、仁王立ちした奴は首を横に振った、断固として僕の訴えを退けるつもりらしい。
「だって、もう限界だよ許しておくれよ」
今度は涙を溜めての、泣き落としにかかる。
「オイ、目薬落としてるぞ、お前古典過ぎ」
「えっ、使って無いから落とす訳無いじゃないか、今日は玉葱だよ」
「頼む、そんな物を仕込んでる暇があるなら、さっさと書き上げてくれ。お前の脚本が上がらないことには、舞台稽古もままならん」
目一杯疲れと呆れを含んだ中に、懇願のスパイスを効かせた声を出している。
いや、僕だって出来る物なら完成させたいとは思ってるんだけど、どう言う訳だか中々思った通りには行かないんだよ。
僕の仕事が終わらなければ先に進めないってことも充分承知してるんだけど、こうしてこんな狭い原稿用紙が散らばった汚い部屋の中で缶詰なんかしても良いものが浮かぶとは到底思えないんだよな。
と、心の中で目一杯言い訳をする。でもこれって毎回のことなんだよね。
僕は芝居の脚本を書くのを仕事にしている。ちなみこの部屋で僕に脚本を早く書き上げろって尻を叩いてるのは、演出家で舞台監督をしている学生時代からの友人の修だ。
僕らがサークルの延長から、面白そうだって言う理由だけで旗揚げした劇団は、その自由発想ってのが受けて、何とか軌道に乗ってそれで飯が食べられる程度に上手くいってる。
もっとも、今現在脚本が上がらないという致命的な問題を抱えていたりするのだけれど。
「限界なんだよ、旅に出る!!」
そう叫ぶと、机の下に隠していた靴をワシヅカミ、僕の前に立ちふさがる敵にタックルをぶちかました。
まさかこんな実力行使に出るとは思わなかった修は、よろけ(力いっぱいぶつかって行ったのによろける程度だったのは、奴の体格と運動神経が良いせいで、決して僕がひ弱な訳じゃないぞ)その隙にまんまと僕は、牢獄のような自分の部屋から逃出す事に成功した。
背後では「バカヤロー、靴隠し持つなんて変な智恵までつけやがって」って言う、怒鳴り声が聞こえけどそんなのは無視だ。
僕は子供の頃から、電車が大好きだった。
休みの度に父に「電車が見たい」とせがんで、家の近所にある列車の車庫へ連れて行ってもらった。
電車に乗ることではなく、その姿を見ることが大好きだったのだ。だから子供の頃の夢は電車の運転士ではなく、電車を作る人で、大人になった今は、電車をいつまでも見ていられる人になった訳だ。
そして、あの汚い部屋から逃出してたどり着いた先は近所から一駅離れた駅のホームだった。一駅離れてるってとこが見つからないようにって言う僕なりの悪知恵を働かせてるのだけど。
僕は、ホームのベンチに座って、列車を何度も見送っている。
何処かへ行きたいのではなく、何処かへ連れて行ってくれる電車が好きなのだ。
そしてその電車に揺られている人達のなんていうのだろう、生活や人生を色々想像するのも楽しかったりする。
空想の世界にいつでも出かけられる僕は、実にお手軽なレジャーの達人だ。
自分にとっては楽しい旅、他人から見たら電車に乗る訳でもないのにずっと駅のホームに居る奇妙な暇人、ってのを二時間程続けていたのだか、そろそろそれにも飽きた頃、隣のベンチに座る男の人に興味が湧いた。

|
|
|
|